2025年 NHK大河ドラマにまた、新しい人物が登場です。
その名も、平沢常富。
なんと、「平沢常富を探せ」が「ウォーリーを探せ」のようにテーマになっています。
蔦屋重三郎が探しており、その結果、朋誠堂喜三二、となりました。
「べらぼう」の中では、尾美としのりさんが活躍しています。
平沢常富とは朋誠堂喜三二のこと?
平沢常富(ひらさわつねとみ)、この名前が本名です。
そして朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)は戯作者としての名前、つまりペンネームです。
平沢常富は、若い時から文学好きで、俳句や漢文を習っています。
ある藩の武士であったため、江戸勤めとなり、江戸の文化に触れて、芝居などの芸術、吉原のとりこになりました。
芝居、文学好きがだんだんと自分も、本を書き出すようになり、戯作の世界にすっかり夢中になり、江戸での文壇デビューとなりました。
文学好きが、作家への道を開いたのですね。
朋誠堂喜三二が、好んで書いたのは、黄表紙本(きびょうしぼん)。
そして、言葉遊びをたくさん取り入れた知的な香りがしながらも、洒落た風俗描写が特徴な、本を次々、書いていきました。
平沢常富さんは、非常に江戸の快楽的な空気が気に入った、作家だった、と思います。
| 「黄表紙本」とは?
江戸中期〜後期に出版された、挿絵入りの小説本です。庶民を読み手として対象としているため、軽快で、風刺も込めた内容になっています。 ユーモアを取り入れた滑稽話です。 表紙が黄色い紙で装丁されていたから「黄表紙」と呼ばれました。 この時代の本は、黄表紙以外にも、赤、青、黒の装丁の本があって、それぞれ内容位によってジャンル分けされています。 |
戯作者、平沢常富でしたが、晩年は狂歌作家ととして活躍するのようなりました。
松平定信の寛政の改革を、風刺したような「文武二道万石通」(ぶんぶにどうまんこくとおし)と言う作品を書い他ことから幕府の目に留まり弾圧されたからです。
この本は、鎌倉時代の話を書いたものですが、当時の話を、松平定信の改革に例えたので、幕府から目をつけられる結果になってしまいました。
平沢常富の歯並び?
平沢常富の「歯並び」について、SNS上で話題になっています。
平沢常富の歯並びが悪いのか?と思ったらそうではなく、キャスティングされている 尾美としのりさんのこと、とありました。
しかし、その歯並びも演出、と言う声もあります。
果たしてどっちでしょう?
平沢常富は秋田藩士だった?
平沢常富は、秋田藩の藩士でした。秋田藩(久保田藩、と及ばれる) 藩主は佐竹家でした。
しかし元から秋田藩士ではなく、江戸の西村久義(にしむらひさよし)という武士の三男として、1735年に生まれました。
平沢の家は、常富の母の親戚です。平沢家は、は秋田藩で、藩主 佐竹家に仕えていました。
平沢常富、江戸留守居役
その流れで、平沢常富は、秋田藩から江戸の留守居役を命ぜられて、江戸にきました。
留守居役というのは、藩が江戸に置いた駐在役人のことで、江戸藩邸を管理したり、幕府との交渉、また情報を取ることが役目でした。江戸時代の外交のような役割ですね。
天明の頃(田沼意次の時代)は、なかなか有能な勤めぶりでした。
というのも、江戸の留守居役では筆頭だった、ということからも想像がつきます。
功績としては、他藩との国境争いを解決した、というから、なかなかのやり手だったのでしょうね。
平沢常富、「宝暦の色男」になった?
平沢常富は、自らを「宝暦の色男」と名乗っていました。
自称というのだから、他人から見るとそんな色男ではない、ということですね。
残されている平沢の肖像画を見ても、それほど色男、には見えませんが、江戸時代と現代では感覚が違うからかもしれません?
「宝暦」年代は1751年〜1764年の頃。これは田沼意次が老中になる前だから、平沢常富の若い頃のことです。
平沢常富は、江戸屋敷に来た頃、情報収集のため、吉原にも出入りしていました。吉原は江戸時代の社交場所でもあったからです。
吉原が気に入った背景には、平沢常富は、文学や俳句など文化に大変興味があったことも一因です。
せっせと吉原通いに励んだのは、勉強というより、趣味から来たものかと思われますが。
色男、というからには、平沢常富は吉原でそれなりの人気があったのでしょう。
文学好き、俳句など好き、というから洒落た粋な人物、が想像できます。
吉原にも、5代目瀬川のように、文学が芸術が得意な遊女がいましたから、そういう人たちにとって、楽しい相手だったと思います。
平沢常富は実はエリート藩士だった?
平沢常富の文学ずきは、教養の高さを物語っています。
吉原に行っても、自分の仕事から外されることもなく、ずっと江戸留守居役を務めていたことからも、藩では重要視されていた人物だったのではないでしょうか?
一般大衆的な者ですが、文学作品も作ったということは、世の中のものごとをよく心得て、しかも文章力も高かった、のですから、平沢常富はかなり頭の良い人物だったのです。
これはやっぱり、エリートということですね。
平沢常富 役 尾美としのり!
「べらぼう」では、平沢常富役は、尾美としのりさんにキャスティングされています。
尾美としのりさんといえば、ほっこりした雰囲気を感じられる役者さんです。
ほっこりした、以外にも、ひょうきんな役も有名で、かつて「鬼平犯科帳」(中村吉右衛門 主演)で、部下の木村忠吾 役で人気がありました。
その鬼平こと、長谷川平蔵の若い頃、という人物も登場していて、面白さを感じます。
尾美としのりさんは、その「鬼平〜」の頃とはガラッと違った、人間的深さも感じられる役柄を演じておられるのは、役者としても器を感じます。
腕のいい役人でありながら、遊び人風となり、そして、物書きでもある3つの面を演じている「べらぼう」というドラマでの活躍が、これからも楽しみです。
平沢常富と蔦屋重三郎、どんな付き合いになるの?
平沢常富は、人気の戯作者だから、当然 蔦重こと蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)と関係はありまいすよね。
しかし、最初は、平沢常富は蔦重ではなく、鱗形屋孫兵衛(うろこがたやまごべえ)の、地本問屋(当時の江戸の本屋のこと)で、本を出していました。
その時の 作家名(つまりペンネーム)は 金錦佐恵流(きんきんさえる)。
作品は「当世風俗通」(とうせいふうぞくつう)
この、平沢常富は実は吉原が大好きで、通っているうちに蔦重と知り合い、仲良くなっていきました。
平沢常富がこれから、本を書いて出版していくには、蔦重との連携が外せませんからね。
平沢常富と平賀源内はどのような関係?
「べらぼう」の所々の場面で、平沢常富は平賀源内と一緒のところが見られます。
じゃあ、仲が良かったのかな?と思われるのですが、実は、それだけ、一緒の場面にいた、だけのことでした。顔見知り程度以外のことはありませんでした。
平賀源内の方も、平沢常富のもう一つの名前、「朋誠堂喜三二」のことを、物書きとして知っているだけでした。
だから、蔦重が計画した本の序文を書くことを、断った平賀源内は、自分の代わりに「朋誠堂喜三二はどうだ?」蔦重に推薦したのです。
噂では、平沢常富が、『平賀源内から文章をかく手ほどきを受けた』とありますが、その史料は見当たらず、噂にすぎません。
確かに平賀源内には、たくさんの弟子がいましたので、その可能性はゼロではありません。
残っている文献などでは、平賀源内と直接の師弟関係にある者だけしか書かれていないので、ちょっと、一言アドバイスだけのことなら、伝わっていないのも当たり前ですけれど。
平沢常富の死去はいつ?
平沢常富が死去したのは、1813年6月18日。生まれが、1735年なので、75歳まで生きました。
一般的に、江戸時代中期の男性の平均寿命は、30〜40歳と言われています。
ですがこの数字は乳幼児の死亡率が高いため、30〜40と出ており、実際に乳幼児期を生き抜いた男子では66歳ほど生きらる、という統計もあります。
その事情を考えると、平沢常富の死亡年齢は、長い方になりますね。
死因についての、公的記録はありませんが、年令を考えると、老衰、といって大丈夫と思います。
平沢常富を探せ、とは?
なぜ、「〜探せ!」」とか「〜どこに」と平沢常富は言われるのでしょう。
「べらぼう」で特に、話題になったことです。
それで、「平沢常富を探せ!」となりました。
ちょうど「ウォーリーを探せ!」のような感じになっていますが、SNSでは「オーミーを探せ」になってブレイクしました。
これは脚本家の森下佳子さんの、すぐに正体を出さなkった手腕が効いています。
それは、ドラマのオープニングのクレジットに名前が出てくるのに、実際にどこにでてく流のか、ドラマが始まった後で、見つけられないからです。
その俳優らしい人が、写ったかと思うと、ほんの1秒程度だったりするのですから。
ここで、平沢常富がどこのあたりで出てきたか、調べてみました。
- 第2話 10秒程度の出演時間。ちょっと長めですが、顔ははっきりとわかり、テレビの表示を字幕にすると、ちゃんと「平沢常富」と名前が出ます。
平賀源内に「源内先生、その節はお世話になりました」とセリフを話しています。ここでの、平沢常富の姿は、武士風でした。
- 第3話 蔦重が作り上げた「吉原細見」がヒットし、吉原が賑わい、蔦重と つた丸 が喜び合っている場面の、ずっと後ろの方で、平沢富常と似た着物を着た人がいる。
- 第4話 蔦重が呉服屋旦那の集会(宴会)で、錦絵を作る話を持ちかけるが、彼らからの同意はもらえず、失意のうちに夜道を変えるときのこと。
そこで、蔦重は「くそっ!」と声を上げるのですが、その声を聞いて驚く通行人がいました。それが、平沢常富らしい、シルエットを浮き出していました。時間にして、2秒。
- 第5話 吉原に戻ってきた蔦重に対し、義兄(駿河屋の実の息子)が「俺は働きすぎて、おかしくなりそうだ」とぼやいている場面。その前を通り過ぎる武家が、平沢常富っぽいです。ほんの1秒ほどです。
ほんの少しつづの露出が、視聴者に気を持たせ、そして、平沢常富に対する期待を持たせることになりました。
まとめ
平沢常富という人物を見ていると、生活に困って大衆ウケする本を書いたわけではない、ということです。
ということは、本当に楽しい読み物が好きな人物だったといことがわかります。
そして、情報収集と称して、吉原通い。さらに、俳句なども好き、というまさに人生を楽しむエピキュリアンだったのですね。
また、平沢常富 本人の仕事ぶりも認められており、まさに時代を楽しむ人物だったようです。
こうやって、楽しみを知る人が目一杯楽しめるのが、田沼時代の良いところでもあったのだな、と思わせる面がkの「べらぼう」にあります。

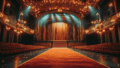

コメント