江戸時代、日本最北の藩といわれた、松前藩の藩主、松前道廣が登場します。
日本全国にいた江戸時代の殿様の中では、マイナーな人物です。
非常に感情豊かな殿様で、江戸でも、自分の国でもいろいろ問題を起こします。
ここでは、松前道廣はどんな殿様だったか、性格はどうだったか?に注目して、マイナーな殿様を生き生きと活躍させてみました。
ドラマの中では、えなりかずき が熱演ぶりが注目を集めそうです。
松前道廣の性格?
松前町史などで、語られていることは、松前道廣(まつまえみちひろ)は派手好き、傲慢な性格だったということです。
単に傲慢だけでなく、子供の頃から文武共に優れていました。
文武に優れている、ということは将来の藩主としての資質がある、とみなされていたのでしょうね。
だから、周りから持ち上げられた結果が「傲慢」となってしまったような気がします。
傲慢、よくいうと押しが強い、つまり強行手段を取ることがある、という面もあります。
松前では、豪快な殿様と言われていました。
のちに、やってきたイギリス船には「イギリスと戦う!」という姿勢を見せた藩主は、藩の民衆には頼もしく見えたかもしれません。
なにしろ、イギリス、という使用人は当時の日本人にとっては全く理解を超えた人たちだったので、
恐ろしかったと思えるからです。
この性格のおかげで、藩は、替えられ、道廣は隠居に追い込まれます。
蝦夷地という江戸から遠いところにいたせいで、中央からの束縛を感じにくかったことで、自由な発想をする人間になったのかもしれませんね。
また、蝦夷地(北海道)という田舎の土地にいるために、たまにしか行かない(6年に一度)での、はなやかな空気に心が舞い上がったでしょうか?
松前道廣、どんな人?
徳川家 10代目将軍 徳川家治の時代の人物。
松前道廣は、7代藩主の松前資広(すけひろ)の長男として生まれました。
1765年10月、父 資広の死後11歳で 松前藩の藩主となりました。
松前道廣、ちょっとヤンチャな殿様?
遊び人だったようで、吉原の遊女を妾にする、など、素行がいいとは言えず、遊女に入れ込んだのでしょう、借金も多かったです。
借金が多く、藩の財政が傾きそうなので、幕府からは注意を何度も受けています。
注意してくれるなんて親切な面が幕府にあったのですね。
大抵は、借金があるとわかると、問答無用で取り潰される藩もあったことと思いますが。
また、将軍が家治の時代、家治に批判的だった、一橋治済(ひとつばしはるさだ)や伊達家、島津家、その他の国学者と交友関係がありました。
松前道廣、戦好きの殿様?それとも目立ちたがり屋?
「べらぼう」では、えなりかずきがキャスティングされ、従来のえなりかずきとは一味違う、役となりました。
「えなりかずき」の名前が「えなりかず鬼」なんて言われるほどはっちゃけてます。
実際は、ここまではっちゃけている、という殿様ではありませんでした。
松前道廣、海外交渉は苦手な殿様かも?
松前藩は、北海道にあるため、ロシア、またそのほかの西洋諸国とのの関わり合いも出てきます。
ロシアからは、通商の要請がありましたが、松前道広は拒絶していました。
理由は、幕府が許さない、と言ってです。
めちゃくちゃな外交政策ですね。今日では考えられない行動です。
松前道廣は対外政策が苦手?とも思われるのですが、日本そのものが外国に慣れていなかったので、仕方ないことではあったのでしょう。
幕府は、幕府自体がはっきりと拒絶していたわけではないので、松前藩のいさみあしでした。
1796年には、エゲレス(イギリスのこと)の船 プロビデンス号がアプタ沖に現れた時、鎧を着て出陣した始末です。
この時の松前道廣は、隠居しており、藩主となっていた息子や家臣たちが全員反対したにも関わらずに、です。
アプタ沖とは現代の、北海道虻田郡洞爺湖町(あぶたぐんとうやこちょう)で、松前より北に約230キロほど離れています。
高速道路も通っていない江戸時にそんな遠くまで、すっ飛んでいくとは、かなり、はっちゃけた殿様ですね。
それとも戦争好きだったのでしょうか?または、自分の力を見せつけるのが好きな殿様か?
松前道廣が、引退をさせられたのはなぜ?
性格が、奔放で、政策も直情的でスタンドプレイが目立ったところが、幕府からみて危うかったのです。
松前道廣が、第一線から引くようになったのは2回あります。
まず最初は1792年。この時は、クナシリ・メナシの戦いというアイヌの反乱が起き、平定することができましたが、幕府に、「松前藩は頼りない」と思われて、しまいました。
そこで、1792年、松前道廣は隠居し、藩主の座を息子 章廣(あきひろ)に譲っていました。
しかし、それだけではじっとしていられなかった性分だったのでしょう。
1796年、イギリス船プロビデンス号が、虻田沖(今の洞爺湖町)に現れた時、隠居の身であるにも関わらず、出陣していきました。
家臣たちに、相談も、対策も立てないまま、ただ鉄砲玉のように飛び出していったものだから、幕府からもお叱りを受けてしまったのです。
1807年に、松前道廣は、永蟄居(えいちっきょ)と呼ばれる謹慎を申し渡されます。
その時の理由というのが、藩主である時代に道廣がとった、強硬策 特にクナシリメナシの戦いに至るまでの経緯、そして不良らしい行動が処罰対象になったのですが。
この、イギリス船に向けての、無許可で出撃したことも、関係あるのではないかと、私はみています。
松前道廣は、蔦重とどんなつながりが?
松前道廣も、弟の蠣崎波響と同じように、蔦屋重三郎と交友があった、という史料はありません。
しかし、松前道廣の行動を見てみると、江戸で遊んだり、大金を使ったり、遊女を妾にするなど、吉原に出入りした様子が見られます。
吉原といえば、蔦屋重三郎。「べらぼう」に登場するのだから、蔦重と関係ないわけないでしょ、と思うのです。
「べらぼう」では、こちらも自由な考えの持ち主の蔦重ですが、もしかしたら、松前道廣はその上をいく、飛んでいる人物かもしれません。
そんな設定の、「べらぼう」は面白い展開になるでしょう。
松前道廣、弟の蠣崎波響との兄弟仲は?
松前道広には、蠣崎波響という画家の弟がいました。といっても母親は違います。
そこで、二人の兄弟仲がどうだったか?ということは残念ながら史実として残されていません。
弟は家老の家、蠣崎家に養子にいき、そこで家老、画家としての生涯を送りました。
大河ドラマ「べらぼう」で、松前道広と蠣崎波響のどちらもが出演するところから、二人の仲が気になるところです。
「べらぼう」で、どうなるか予想しながら、二人の兄弟仲を探ってみましょう。
兄 道廣は1754年生まれ、一方 弟 蠣崎波響は1964年生まれ、10歳ほど歳が違います。
松前道廣は、藩主であるから、参勤交代(さんきんこうたい)江戸に行きます。
松前藩は、遠いという理由でしょうか、6年に1回の参勤交代でよかったのでした。藩によっては毎年行かなければならないところもあるので、楽とも言えるでしょう。
しかし、松前道廣の性格を考えると、一度江戸の華やかさに触れて仕舞えば、江戸は離れがたいところに見えたかもしれませんね。
道広は吉原の遊女に惚れ込んで、遊ぶはもちろんのこと、自分の妾にしています。
一方の、蠣崎波響も絵の勉強に、1773年に蠣崎波響は江戸に行っており、その時の道廣は29歳。
蠣崎波響は9歳の時に江戸に来て、20歳を過ぎるまで滞在していました。
これだけいれば、弟の江戸滞在中に、兄 松前道廣が、参勤交代で江戸に来た、というあらすじは、十分にアリです。
弟は、松前藩にとって側室の子供で、家老の家に養子に行ったものだから、松前道広には、蠣崎波響の存在は、弟としてより、家老としての意識が強かったのではないでしょうか?
「べらぼう」のストーリーに蠣崎波響が、吉原の遊女に振り回されるエピソードがある、というのは、兄 松前道廣のことで悩まされたのではないかと推測されます。
松前道廣 出身の松前藩とは?
現在は当たり前のように、観光地となっていて、「日本最北の藩」とか「桜の名所」、言われています。
当時は、米のできない土地でした。その中ではどうやって国の財産を決めていたのでしょう?
また、松前藩の起源はどうなのでしょう?
松前道廣の国 松前藩、米のできない土地
北海道では当時、寒冷地すぎて米を作ることができませんでした。
江戸時代は、藩の生産量を 石高という米の生産量で藩の規模を決めるのでしたが、それができず、別のやり方で決められていました。
松前に決められた石高は、1万石。これは、江戸時代の最低基準額でした。
つまり米が取れないから別のやり方で年貢を集めると。
それは交易でした。当時からアイヌとの交易があり、その取引量で計算するのです。
主な物品は、乾物(昆布、干し鱈など)、ラッコの毛皮でした。
米を収めることは免除されていたので、使役として、北海道全土の警備を任されていました。
北海道は広すぎるので、完全に目を行き届けさせるのは難しい、と思われます。
松前道廣の国 松前藩の家系は?
1454年、武田信広(たけだのぶひろ)という人物が初めて、蝦夷地に渡ったことから始まります。
「武田」というから「武田信玄」の家系か?と想像する方も多いいと思いますが、信玄とは関係ありません。
松前藩の先祖の武田氏は、室町時代の武将でした。
信広の家系については、その始まりがはっきりしていません。
室町時代、武田の家のものが、若狭国を出て、東北を支配していた南部藩に仕え、そこで蠣崎の土地を与えられ、北海道(蝦夷地)に渡った。
また、蝦夷地の同じく南部 下の国(しものくに)を支配していた、安東氏(あんどうし)の元に武田の一族のものが婿となって蠣崎を名乗った。
という説が有力ですが、どれも確証が取れていません。
武田信広は蠣崎の姓を名乗るのは、江戸時代となり1604年、徳川家康から松前という名字をつけてもらい、以来「松前」となりました。
江戸時代の、北海道(蝦夷地)がどのようなものだったかは、こちらの記事に詳しく書いてあります。
まとめ
非常にマイナーな殿様ですが、この人の動きには多くのものが、翻弄されることとなりました。
これは本人の性格によるものなのか、あるいは、日本の目立たない国の殿様の悲劇なのでしょうか?
それでも、自己主張の強い殿様には好感がもてます。
それでも、あまりにも日本の隅っこに国がありすぎて、中央の情報が伝わりにくい、ということがよくわかります。
現代のようにインターネットが発達していなかった、江戸時代、どうやって中央の意向を読み取るのか?注目していきましょう。


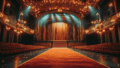
コメント